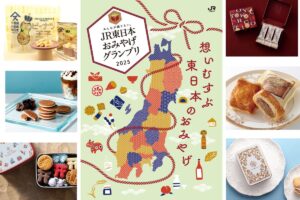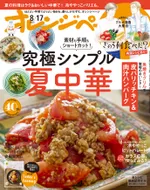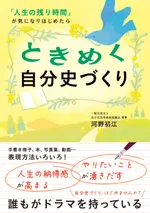山内マリコ×オレンジぺージ創刊40周年記念書きおろしエッセイ/謎解き『オレンジページ』
山内マリコ
謎解き『オレンジページ』
『オレンジページ』といえば、母だ。
わたしが実家にいた頃だから、もうはるかはるか、遠い昔のこと。うちには家族がそれぞれの好みで買ってくる雑誌がいろいろ転がっていたけれど、なんと言ってもわたしが断トツで雑誌好きだった。完全にトリコだった。
ティーン向けのファッション誌、少女漫画雑誌、映画雑誌。毎月の発売日を、クリスマスを待つくらいのテンションで待ちわびたものだ。新しい号のページをめくるときはいつもアドレナリンが出た。雑誌を抱きしめてくるくる踊りだしそうな勢い。あの感覚は、大人になってからはついぞ味わっていない。
十代のわたしが雑誌に傾けるパッションに比べると、母のそれは低温だったと言わざるをえない。なにしろ家にある『オレンジページ』を母がめくっている姿はあまり記憶にない。わたしがひと月で雑誌をぼろぼろになるほど読み込んだのに比べると、母の『オレンジページ』はどれも、さほどくたびれてはいなかった気がする。買ったときとほとんど同じきれいな状態のまま、ずっとあった。『オレンジページ』はただいつも家にあり、それは家庭の風景の一部だった。
これは別に、母が『オレンジページ』を愛していなかったということではない。当時の母と同じ年代になった今なら、大人は十代の熱量で雑誌を読まないことがわかる。家族のケアを一手に引き受けていた母にすれば、のん気に雑誌を読み込むような余暇時間は、なかったということも。
『オレンジページ』はたしかにそこにあった。テーブルの上に、新聞と一緒に積まれていた。そこに女性週刊誌が加わることもあった。母は雑誌を毎号買っていたわけではなくて、とても気まぐれに購入する。たまに父に本屋さんに連れて行ってもらったとき、「お母さんにもなんか買っていこう」と提案されることがあり、そういうときはわたしが『オレンジページ』を選んだ。
けれど母が『オレンジページ』に載っていたレシピでなにか作ってくれた、という記憶も実はあまりない。母はよくテレビの料理番組を見ながら熱心にメモをとっていた。けれど、そのメニューが食卓に登場することもほぼなかった。母はあまり料理が好きではなく、定番の献立がぐるぐるルーティンで巡った。
レシピとして活発に活用したわけでもなく、コラム欄などを読み込んだわけでもない。それじゃあ、あの『オレンジページ』は、母にとってどんな存在だったのだろう。
『オレンジページ』の創刊は一九八五年。わたしが幼稚園から小学校にあがるくらいの時期だ。当時の母は三十代半ば。
うちは田舎にしてはめずらしく祖父母と同居していない、気楽な核家族だった。家族はみな誰に気兼ねすることなくのびのび過ごしていたけれど、それはつまり、母だけがのびのびしていなかったということだろう。〝母親〟という役割を手探りで演じていたというか。
お姑さんにこうしろああしろと指図されるのではなく、自由裁量で〝母親〟をやる。昭和は、子どもにまつわる全責任を母親が背負わされた時代だから、そのプレッシャーたるやすさまじかったに違いない。母親としての「正解」の振る舞いがわからないまま、毎日の食事作りに追われる日々。
そんなときに『オレンジページ』は創刊された。本屋さんではじめて『オレンジページ』を見つけたとき、母の目にはきっと、これは自分のための雑誌と映ったに違いない。なにしろソーシャルメディアのない時代、雑誌が醸す独特の「紐帯(ちゅうたい、二つのものをかたく結びつけるもの)」のようなパワーは、今からは想像できないほど強かった。
家庭という、それぞれが独立国家みたいに孤立した小さな社会の中に、母たちはいた。横のつながりを作ることは難しく、自分たちの属性を確認し合える場もない。
その状況をなんとかしようと動いた女性たちがいた一方で、別のものに救いを求めた女性たちもいた。これは後々知ったことだが、この時代に隆盛した新宗教は、専業主婦たちの孤独感につけ込んだという。
あの頃の母にとって『オレンジページ』は、主婦である自分……とりわけ〝専業主婦〟である自分の、よりどころみたいに機能していたんではないか。
『オレンジページ』をとおして、自分たちがつながっていることを確認して、心を慰められていたのではないか。
それがあるだけで、そこにあるだけで、支えになる。『オレンジページ』は、そういう存在だったのではないか。
『オレンジページ』が創刊されて今年で四十年。
二年前に当時の編集長と、連載小説の打ち合わせをしたときのこと。驚いたのが、アンケートから見えてきた『オレンジページ』の読者像だ。多くが仕事を持ち、外で働く女性だった。わたしが子どもだった頃とは様変わりしている。社会はゆっくりと、確実に変わっているのだなぁと思った。
けれども、『オレンジページ』が持つ〝よりどころ〟としての機能は、母の時代からあまり変わっていないのではないか?
わたしにはそんな気がするのだった。

山内マリコ(やまうちまりこ)
1980年生まれ。富山県出身。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。2012年『ここは退屈迎えに来て』で小説家デビュー。これまでに同作と『アズミ・ハルコは行方不明』『あのこは貴族』が映画化されている。その他の著書に『一心同体だった』『逃亡するガール』、エッセイ『きもの再入門』など。小誌『オレンジページ』にて「陽子さんはお元気ですか?」を連載中。

次回エッセイは6/17(火)更新。角田光代さん『ともに40周年!!』です。お楽しみに!