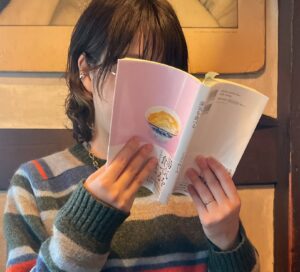いりこと鰹の合わせ出汁でじっくり煮込む、休日おでん

秋を飛び越えて、一気に冬の気配を感じるようになりましたね。
キュッと冷え込む夜に、つい食べたくなるのがおでん。
普段は面倒くさがりでズボラな私ですが、せっかくの休日くらいは、イチから出汁をとって美味しいおでんを作ってみよう!ということになり、この日は夫と一緒におでんづくりを楽しみました。
ああ懐かしい、いりこと鰹の香り
今回は、いりこと鰹から出汁をとることに。
※ここに昆布を加えると相乗効果で旨味がさらに増すのですが、甲状腺疾患があり昆布の摂取を控えているため、我が家では昆布なしの出汁をとることにしました。
素材の香りが、湯気を伝ってふわっと鼻に届く感覚。
実家で母や祖母が、夕方にぐつぐつ煮炊き物を作ってくれていた頃を思い出して、なんだか懐かしくほっこりしました。
こんなに手間のかかることを毎日してくれていただなんて、愛だなぁ。と感謝したと同時に、私もこれからはもう少し出汁をとって料理する日を増やそうと思うのでした。
いりこと鰹の出汁の取り方
- いりこの頭と内臓を取り除く(約30グラム)
- 鍋に常温の水を1リットル入れ、処理したいりこを浸して1時間半〜2時間程度おいておく
- 鍋を中火にかけて、沸騰したら灰汁を取り除く
- さらに弱火で5分ほど煮出し、火を止めていりこを取り除く
- 火を止めた状態で、花鰹約30グラムを加えて自然に鍋底に沈むまでおいておく(1〜2分で沈みます)
- ザルにキッチンペーパーを敷き、ボウルにセットして出汁を濾す。


お互いの育った味を掛け合わせて
出汁をとり終えたら、醤油・塩・砂糖・みりん・酒で味を調えて、いざ具材を投入。
「牛すじは入れるっしょ!」
「鶏肉じゃなくて、手羽元の方がいい出汁でるよ!」
「もちろん、じゃがいもはマストよね?」
私と夫それぞれが幼い頃から親しんできた具材をああだこうだ言いながら厳選し、掛け合わせながら、我が家のおでんを作り上げていくのでした。こうやってまた新たな「家庭の味」がつくられていくのですね。
ちなみに今回は、
卵・大根・にんじん・じゃがいも・ちくわ・ごぼう天・厚揚げ・こんにゃく・もち巾着・牛すじ串・手羽元
と、たくさんの具材をたっぷりじっくり煮込みました。

手間暇かけてつくるごはんって、やっぱり美味しくてしあわせ
それから数時間ぐつぐつ煮込み、味を染み込ませてできた我が家のおでん。
まだもう少し煮込んだほうが、さらに味が染みて美味しくなりそうでしたが、それはまた明日のお楽しみ。
出汁が染みた具材に練り辛子をつけて食べると、出汁の風味がより華やかになって口いっぱいに広がりました。
牛すじと手羽元からもさらにいい出汁がでたので、「出汁の風味を豊かにする」という視点で具材選びをしてみるのも楽しいかもしれないです。

出汁から丁寧にとって作るおでんは、ちょっと手間がかかるぶん、美味しさと満足感は何倍にも増します。
さらに大切な人と一緒に作れば、お互いの育った味を知りながら、温かい気持ちにもなれる素敵なひとときにもなるはずです。
おうちでのんびりする休日には、ぜひみなさんも普段よりひと手間加えたおでん時間を楽しんでみてください◎