
老と介護と[姥捨山]

同世代の友人、仕事仲間に隣近所、
此処ドイツでも会うたび出てくる親の話。
30代、40代の頃には上がらなかったテーマです。
それもその筈
50代後半にもなると親も80オーバー。
末っ子であるクマ夫の母親ともなると90歳。
要介護1から2になった。ウチは3になった。
施設は1年待ち、幾らする?
デイサービスを嫌がる、歩行器を意地でも使おうとしない。
目が殆ど見えないのにテレビ雑誌の契約を止めない。
『頑固』この単語を誰もが使い、ため息をつく。
そんな話を聞く度、子供達の足枷になるのだけは避けたい。
そうなる前にポックリ逝きたいと切に願うのです。
義母ょ、貴方もそう思っていたのか?
義母の室内用歩行器画像の背景。
剥がれた壁紙は、3階に住む90代独居老婆の洗濯機の水が
1階の義母の台所とリビングにまで流れ出したため。
1ヶ月経っても終わらぬ工事
上と下の独居老人に挟まれた、2階に住む若者はサポートに追われ
てんやわんやだったと嘆いておられました。
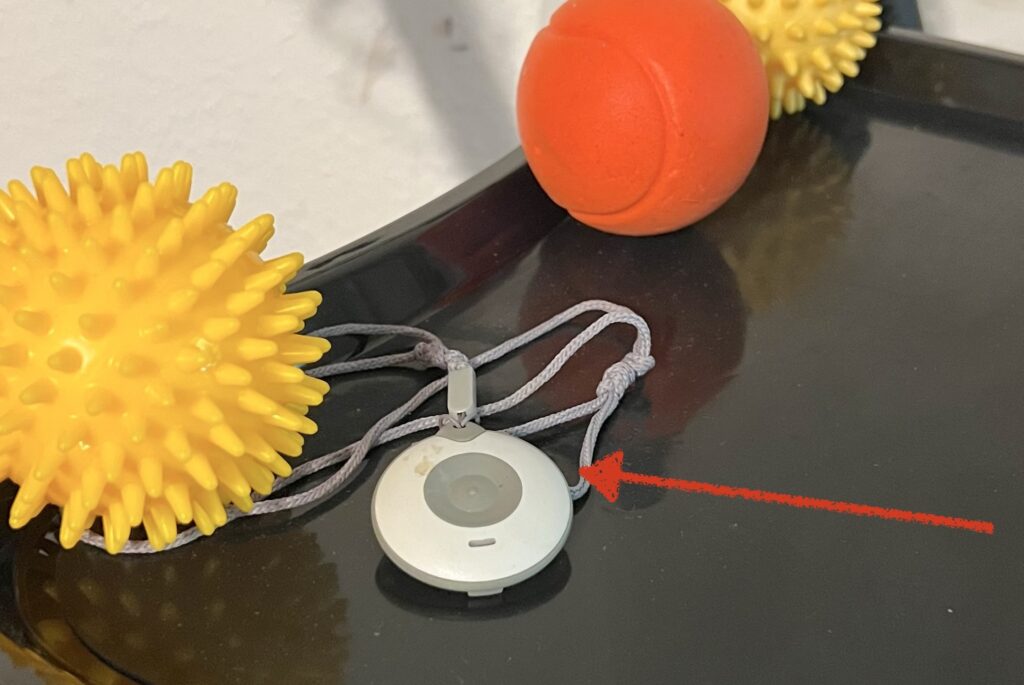
ふと、1976年放送、日本昔ばなしの『うばすて山』
を想い出し調べてみると、山へ捨てられるのは60歳。😨
姥というからには女性限定であり、
私も姥捨山行きのバス乗車は3年を切っています。

いつ何時、寿命を迎えるやもせぬ。
一回でも多く好きなものを胃袋に収めておかなくちゃ。
どうして、そこへ発想が飛ぶ?
呆れるクマ夫でしたが、お寿司大好物の子供達は大喜び。
車で20分、魚屋さんへと飛んで行きました。
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
街中で見かけた品の良いマダムが引いていた
福祉国家・デンマークのオシャレな歩行器
https://www.byacre.com/de/rollators/































