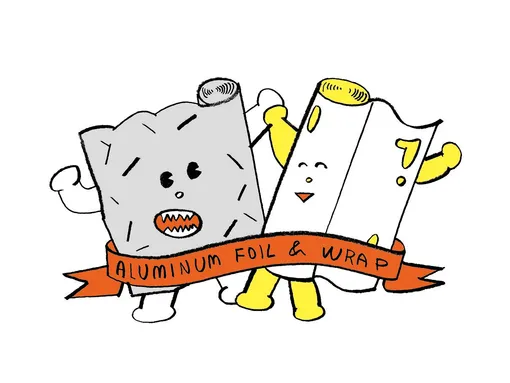【防災の日】改めて知りたい在宅避難。災害レスキューナースが教える心得7カ条とは

9月1日は「防災の日」。地震や台風などの災害は、特別なことではなく今この瞬間に起こるかもしれない出来事です。そんな「もしも」のとき、避難所には行かず、自宅にとどまる「在宅避難」という方法も。
実際、避難所は収容人数に限りがあり、多くの人が自宅での避難を余儀なくされます。より安全に自宅で過ごすため、今回は災害レスキューナースとして活動する辻直美さんに、在宅避難の備えと心得を伺いました。
「在宅避難」はココがイイ!

震災や水害の際、自宅が安全で住み続けられるなら「在宅避難」が推奨されています。ライフラインが止まれば大変なことも多いですが、慣れた家で過ごせる安心感は何にも代えがたいもの。ほかにも、さまざまなメリットがあります。
住み慣れた家で過ごせる

災害発生時は心身ともに大きなストレスがかかるもの。在宅避難なら慣れた家でいつもの暮らしに近い状態で過ごすことができ、ストレスが軽減。とくに小さな子どもやシニアの負担を減らすことができます。
感染症のリスクが低い

不特定多数の人が集まる避難所では、新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症のリスクが高まります。自宅であれば、家族以外の人との接触を減らせるので、こうしたリスクは減少します。
備蓄品が活用できる

用意しておいた備蓄品(食品等)が活用できる点も、在宅避難のメリット。自身や家族が好むものを備えておけば、非常時であってもほんのひととき、ホッとできる時間を過ごせます。
プライバシーが保てる

避難所は段ボール等で仕切りが作られることはあっても、プライバシーが守られる環境ではありません。過去の震災では、仕切りがないためふとんをかぶって着替えたという人も。自宅ならその点も安心です。
ペットといっしょに過ごせる

避難所によっては、ペットといっしょに屋内に入れず、季節や天候を問わず屋外で世話をすることに。在宅避難なら自宅でペットとともに過ごすことができ、ペット自身もストレスがかかりません。
デメリットもきちんとチェック!
● 二次的災害の可能性がある
● 救助・救援が遅れる
● ライフラインが途切れると、生活の維持がむずかしい
● 水や食料などの配給が届きにくい
在宅避難は残念ながらデメリットも多いもの。それでも、在宅避難を強いられる可能性があるということを忘れないでください。大切なのは日ごろの備え。近隣住民とよい関係を築き、常に地域の災害情報を得られる環境をつくっておきましょう。
在宅避難の心得7カ条
1.わざわざ「非常食」を買わない
日常的に食べるものはローリングストックを。自身や家族が好んで食べるものを多めに。ふだんのストックの「1.5倍量」を目安に備蓄して。
2.「いつもの日用品」を活用
家庭にある日用品を活用することで無駄が減らせる。PPGS(ペットボトル、ペットシーツ、ごみ袋、新聞紙)はあると便利!
3.「いつもの暮らし」で備える
扱い慣れていないと、いざというとき使えないことも。手回しラジオなど非常用に特化した家電ではなく、いつもの暮らしで使えるものを。
4.「避難訓練」を日常にする
月に一度程度でいいので、ガスや電気を使わずごはんを作る&非常用トイレを使ってみる。避難経路も家族みんなで確認を。
5.過剰に「水」を備蓄しない
非常用に水を大量に備蓄してしまうと、期限切れで困ることに。食品だけでなく水もローリングストックを。
6.「情報収集」に時間をかけすぎない
不安なあまりさまざまなSNSやニュースを見てしまうと、フェイクに惑わされる。事前にチェックし、国や自治体の公式アカウントなどから信頼できる情報だけを得るように。
7.「子どもでも扱えるグッズ」を用意する
非常用トイレなどのグッズは、子どもでも扱いやすいものを準備し、事前に何度か使ってみることが重要。収納場所は家族で共有を。
こんなときは、迷わず避難を!

〈家が住めないほど壊れたとき〉や〈そこで生活を続ける自信がないとき〉は避難所へ行く決断もあり。「災害時は心おだやかに過ごせることが大切。避難所は家の最寄りの3カ所くらいを選び、平時に実際に歩いてみて、危険な箇所や段差、坂道がないか確認を」(辻さん)。
食料や水、懐中電灯といった基本的な備えを〈当たり前〉にしておくことが、在宅避難を支える第一歩です。特に睡眠・食事・衛生など譲れない部分は厚く備えておくことが安心につながります。
「助かって終わり」ではなく、その後も安心して生き抜くために。今日からできる小さな備えを、日常の中で少しずつ重ねていきましょう。

国境なき医師団で活動した後、 阪神・淡路大震災を経験。その後、国際緊急援助隊医療チー ムにて救命救急災害レスキューナースとして活動。現在はフリーランスのナースとして、講演や防災教育を行う。
詳細はこちらあわせて読みたい
監修/辻 直美 イラスト/あべさん 原文/和栗 恵 文/池田なるみ