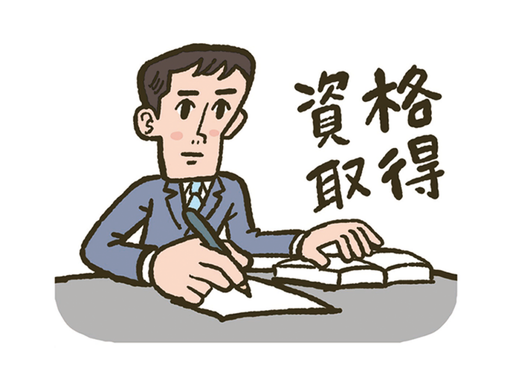【相続トラブルQ&A】遺言書に「長男に全額相続」とあったら、他の人は貰えない?

「うちはもめるほど財産がないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルは遺産の額に関係なく起こる可能性が。
実際、裁判所に持ち込まれた遺産分割案件のうち、33%が1000万円以下、44%が5000万円以下と、どの家庭にも起こりうる身近な問題なのです(※令和3年「司法統計年報」より)。
そんな相続トラブルについて、弁護士の中里妃沙子さんがQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q. 遺言書に「長男に全額相続する」と書かれていた場合、ほかの相続人は1円も受け取れない?
A. 「遺留分」を請求できます

「遺留分」とは、一定の相続人に対し、民法で認められている遺産の最低限の取り分のこと。遺言書の内容にかかわらず、法定相続人は遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分を請求できるのは、故人の配偶者、子ども、両親。遺留分は「法定相続割合の1/2または1/3」と定められていて、その割合はだれが相続人かによって変わります。兄弟姉妹には、遺留分を請求できる権利はありません。
Q.話し合いをしても、遺産の分け方が決まらなかったら?
A.家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てます
相続人どうしの話し合いがうまくいかなかったり、遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。申し立て後は、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、相続人全員による合意をめざします。
Q.故人の介護をしたことは考慮される?
A.「寄与分」を請求できることも
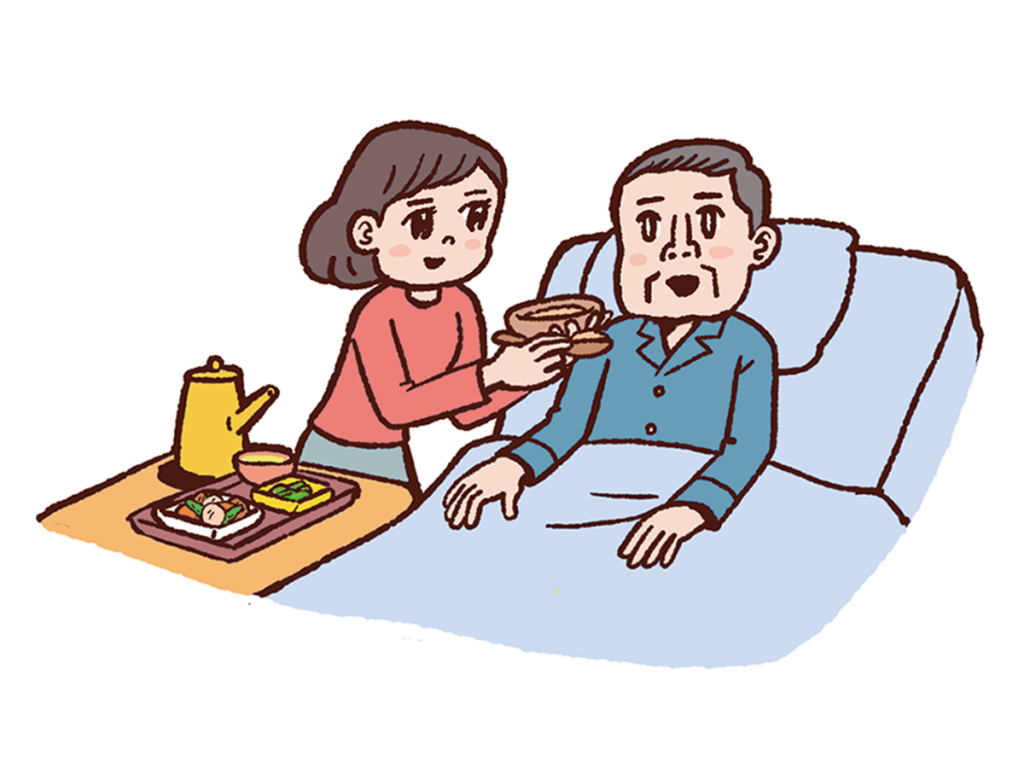
介護や家業の手伝いを無償で行うなど、故人の財産の維持または増加に貢献していた相続人は、法定相続分より多く受け取れる「寄与分」を請求することができます。
しかし、民法では親族間に扶養義務を定めているため、親の介護は扶養義務の範囲内と判断されることが多く、寄与分請求のハードルは高め。2019年の相続法改正以降は、子どもの配偶者(長男の嫁)など相続人以外も「特別寄与料」が請求できるようになりました。
Q.故人から特別に援助を受けていた相続人がいた場合は?
A.「特別受益」として相続分から差し引くことが可能

一部の相続人だけが故人から生前贈与や遺贈で受け取った利益のことを「特別受益」といい、多額の結婚持参金や住宅購入費、大学・留学費用などが該当します。相続人間の公平を図るため、「特別受益」分を相続額から差し引いて計算することが可能です。
ただし、生前に受け取った金銭などが「特別受益」にあたるかどうかの判断は簡単でなく、トラブルの原因となるので専門家に相談したほうがベター。
相続トラブルの解決には、法律や複雑な手続きが関わるため、専門家に相談するのが安心です。早めに弁護士や税理士など、信頼できる専門家のサポートを受けましょう。
※2025年1月8日時点の情報です。

「丸の内ソレイユ法律事務所」代表弁護士。東北大学法学部卒業、南カリフォルニア大学ロースクールLLMコース修了。著書に『弁護士がわかりやすく書いた離婚したいと思ったら読む本』(自由国民社)など、テレビや雑誌などメディア出演も多数。
詳細はこちらあわせて読みたい
監修/中里妃沙子 イラスト/沼田光太郎 原文/太田順子 文/池田なるみ