「しっかり食べなさい!」「野菜も残さずね」。食事のとき、こどもにバランスよく食べさせねば、と義務感に駆られてイライラしたり、しかったりすることはありませんか? そして後から反省……。私も何度も経験があります。
食べ物についての親子の会話が注意ばかりになってしまうと、もったいない!
「食べること」を親子で楽しく話せるように、さまざまな視点から食の歴史をひもとく歴史学者・藤原辰史先生に、 楽しい質問を教えていただきました。
今まで食べたなかで、いちばんおいしかったものなぁに?

「今まで食べたなかで、いちばんおいしかったものは?」
こどもたちにこの問いかけをすると、どんな答えが返ってくると思いますか?
「ママの作ったハンバーグ」 「パパが焼いてくれるホットケーキ!」なんて答えを期待しませんか?
ところがこどもたちの答えは、友達と食べた給食のサイダーポンチだったり、修学旅行で初めて食べた牛タン、 試合に勝ったあとのファストフードのポテトなど、決して「家庭の味」や「手作りの味」という枠の中に収まっていない、ということが多いです。
「何を食べたか」より、「だれと食べたか」
そこに見えてくるのは、人とのかかわりや風景。
「何を食べたか」より、「だれと食べたか」「どんなシーンで食べたか」のほうが、 人生一のおいしさを濃く、深く彩っていることがわかります。 フライドポテトは栄養がかたよっているかもしれない。 でも喜びとともに血となり肉となったことでしょう。食べるということは、 単なる栄養摂取ではなく、 いろいろな人や、さまざまな場所とつながっている。 食べた記憶と経験が、「おいしい」を形作っていくのですね。
ほかには、「犬や猫のごはんと人間のごはん、何がちがうのかな?」なんていう質問はいかがでしょう。
仲間と食べ物を分け合ったり、料理して食を楽しむのは、人間の特徴。人間に近いとされるゴリラでさえも、食べ物は隠して食べるのだそう。人間が「食」を隠さないことを選んだときから、食べ物とエサが区別され、食はだれかと食べるものになったのだと考えられます。
このような質問を、ぜひ、なぞなぞ感覚でこどもに問いかけてみて。 意外なその答えに、〈食べる〉 ことは、こどもの想像力をかき立てる、 楽しく豊かな世界であることに気づくかもしれません。
教えてくれたのは・・・
藤原辰史先生 京都大学人文科学研究所准教授。専門は農業思想史・農業技術史。歴史と飢餓の関係、台所や農業機械の歴史 環境史など、幅広い視点から人と食、農を研究。 著書に『食べるとはどういうことか」 (農文協)、『給食の歴史』(岩波新書)など。
京都大学人文科学研究所准教授。専門は農業思想史・農業技術史。歴史と飢餓の関係、台所や農業機械の歴史 環境史など、幅広い視点から人と食、農を研究。 著書に『食べるとはどういうことか」 (農文協)、『給食の歴史』(岩波新書)など。
関連記事
ニガテ野菜とどう向き合う? こどもの好きキライは自信をはぐくむチャンス!
親子で考える「もったいない」 食品ロスを減らすチャレンジ、はじめよう
「非日常」を楽しむ⁉︎ キャンプ料理でこどもの「やる気」があふれ出す!

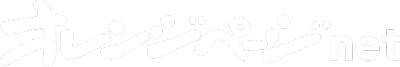 はこちら
はこちら
























