スマホを持たせても、低学年のうちはなくす、壊す、友達や顔見知り程度の人に安易に貸す、充電を忘れるなど物理的な管理ができません。連絡がとりやすくなるというメリットはありますが、ゲーム課金や依存、第三者の誘い出しによる性被害など、深刻なリスクにさらされる確率が高まります。
最終回となる第4弾では、ケータイやスマホを安全に使うためにやっておきたいことを紹介します。
安全に使うためのルール①必要なアプリのみを入れて渡す
家族との連絡用なら、親の古いスマホにLINE アプリだけを入れて渡しても。スマホではなく、家族の共用タブレットにLINEをインストールして固定電話代わりに使うのもよいでしょう。
安全に使うためのルール②ルールは親子で話し合って決める
「◯時以降はさわらない」「就寝時は自室に持ち込まない」「勝手にアプリを入れない」など、話し合ってルールの設定を。使い方に慣れてきたら制限をゆるめるなど、こどもの裁量にまかせる範囲を増やして、信頼関係を築きましょう。
安全に使うためのルール③機能制限して大人がしっかり管理
iPhone には「スクリーンタイム」、Android には「ファミリーリンク」というサービスがあり、スマホの機能や時間を制限できます。TikTok やオンラインゲームなど、アプリをインストールする際は、それぞれのペアレンタルコントロール機能の活用を。
安全に使うためのルール④SNS は家族アカウントで本名を出さない
TikTok やInstagram などは対象年齢が13 歳以上であることを話したうえで、家族アカウントとして開設し、本名は出さないようにします。いつでも大人が内容を見られるようにしましょう。家族アカウントにしておけば、昼夜を問わない友達からの連絡も防げます。
SNS はまず家庭でやりとりの練習を

スマホデビューをして、こどもたちがまず触れるのは「LINE」と考えていいでしょう。しかし、文字情報だけのやりとりでは、「バカじゃん」「消えろ」など、強い言葉の応酬によるトラブルが必ずといっていいほど起こります。話し言葉より書き言葉は強く感じること、形として残るのでダメージが大きくなることなどをアドバイスして、親、次にきょうだいや祖父母、その次に学校の友達など、少しずつやりとりの範囲を広げていきます。
自分がやりとりしている内容をこどもに見せるのも手。実際のやりとりを見ることで具体的な書き方が学べるうえ、「私もお返しに見せようかな」という「返報性の原理」が働いて、こどもも自然に見せてくれます。
『こどもオレンジページNo.8』では、0~9歳のこどもたちとインターネットのかかわりに関する統計データや、専門家によるアドバイスを多数掲載しています。ぜひ書店やWEBでチェックしてみて♪
【その他の記事も参考に!】
◇監修/高橋暁子(たかはし・あきこ)さん
ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNS、10代のネット利用実態とトラブルに造詣が深く、先駆者として、安心な利用方法を啓発。著書に『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社α新書)など。

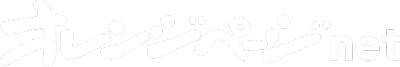 はこちら
はこちら
























