ゲームや動画、SNS。次々と繰り出されるデジタルコンテンツは、刺激的で魅力的。でも、さまざまなリスクもあります。利用のしかたを親子で考えてみましょう。今回から4回にわけて、デジタルツールとのつきあい方をご紹介!
第1弾は、デジタルツールを本格的に使いはじめる前に知っておきたいことを解説します。
後からルールを決めて守るのはむずかしいので、最初に約束を
ひとつの映像を見ているとおすすめに上がってくる関連動画や、展開が気になってしまうゲーム。動画やゲームのしくみは「いかにのめり込んで課金につなげるか」を考えて作られているので、こども自身でやめることは困難です。本格的に機器に触れるようになる前に、家庭の方針を決めてルールを設定しましょう。
手がすくと大人も無意識にデジタル機器に触れがちですが、保護者の使用時間が長いと、こどもの利用が増えるという統計もあります。家族全員で、デジタルツールの使い方を見直してみることも大切です。
アクセスするネットワークは数年ごとに変わっていきます
就学前から、小学校の低学年・中学年・高学年と、数年ごとにこどもがアクセスするネットワークは変化していきます。
①【就学前】多くの子がYouTubeを視聴する

0歳から3歳くらいの間に、多くのこどもが動画の視聴という形でデジタルツールデビューをします。保護者が家事で手を離せないときや、交通機関での移動時などに、子守り代わりに見せはじめて、気づいたら日常的に長時間視聴するようになっていることも。まずは一日の視聴時間を意識し、「一日〇時間までにしよう」と目安を決めて、その時間内でやめる習慣をつけましょう。
マスターしたいこと「時間の制限に慣れさせる」
②【1~2年生】GPS &こども向け携帯電話

学校の授業でデジタル機器を使いはじめます。また、登下校時の防犯目的で携帯電話を持つ子も。しかし、置き忘れや友達との貸し借りといったトラブルが起きがちです。低学年にスマホを持たせるのは時期尚早。まずは機能が限られるこども向け携帯電話や、位置情報が把握できて連絡機能もあるGPS で、こどもがなくさないように管理する練習を。防犯ブザーですむなら、これらも無理に持たせる必要はありません。
マスターしたいこと「端末をなくさないように管理する」
③【3~4年生】TikTok やオンラインゲーム

YouTube だけでなく、TikTokなどのSNS にアクセスし、見るだけでなく投稿を始めるこどもが増える時期です。オンラインゲームを始める子も。しかし、ほとんどのSNSは13歳以上が対象。対象年齢をフライングして利用しはじめてしまっているのが実情です。悪意を持った大人が意図的に接触してくることもあるので、利用するなら保護者の管理が必要不可欠です。
マスターしたいこと「ルールの中で楽しむ」
④【5~6年生】スマホ、LINE デビュー

塾通いを契機に、スマホを利用しはじめる子が増えます。また、小学校の卒業をきっかけに、LINEを始める子も。まだ持たなくてもいい時期ですが、スマホもLINEも使い始めはトラブルがつきものなので、大人が介入できるこの時期に、目をくばりながら使い方に慣れさせていくというのも手です。LINEは家族とのコミュニケーションで言葉の使い方を練習してから、友達とのやりとりを始めましょう。
マスターしたいこと「個人情報を守りながら利用する」
どの年代でもトラブル時にまず親に相談できる関係をつくって
好奇心が旺盛で、あれこれと試行錯誤を重ねるこどもたちは、機器の扱いに慣れるのもあっという間。機能制限をしていても、保護者が想定していない形で見知らぬ人とつながったり、課金したりしてしまうケースも少くなくありません。トラブルは起こりうることだと認識し、どんな問題が発生しても、「まずはお父さんやお母さんに相談しよう」とこどもが思える関係性づくりを心がけましょう。
『こどもオレンジページNo.8』では、0~9歳のこどもたちとインターネットのかかわりに関する統計データや、専門家によるアドバイスを多数掲載しています。ぜひ書店やWEBでチェックしてみて♪
◇監修/高橋暁子(たかはし・あきこ)さん
ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNS、10代のネット利用実態とトラブルに造詣が深く、先駆者として、安心な利用方法を啓発。著書に『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社α新書)など。

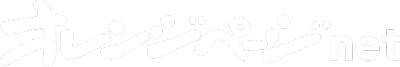 はこちら
はこちら
























