パソコンやタブレットがごく身近にあり、いつでも楽しめる昨今のこどもたち。デジタルツールは、単に楽しみを得るためだけでなく、友達との関係を深め、いろいろな情報を得るために欠かせません。とはいえ、あふれる情報の海のなかでおぼれないように親が工夫をすることが大切です!
第3弾は、動画とゲームにハマりすぎないための工夫について解説します。
第1弾では、「本格的に使いはじめる前に知っておきたいこと」を解説!
第2弾では、「動画とゲームを楽しむための3つのこと」を解説!
こどもの意思だけでコントロールするのはほぼ不可能
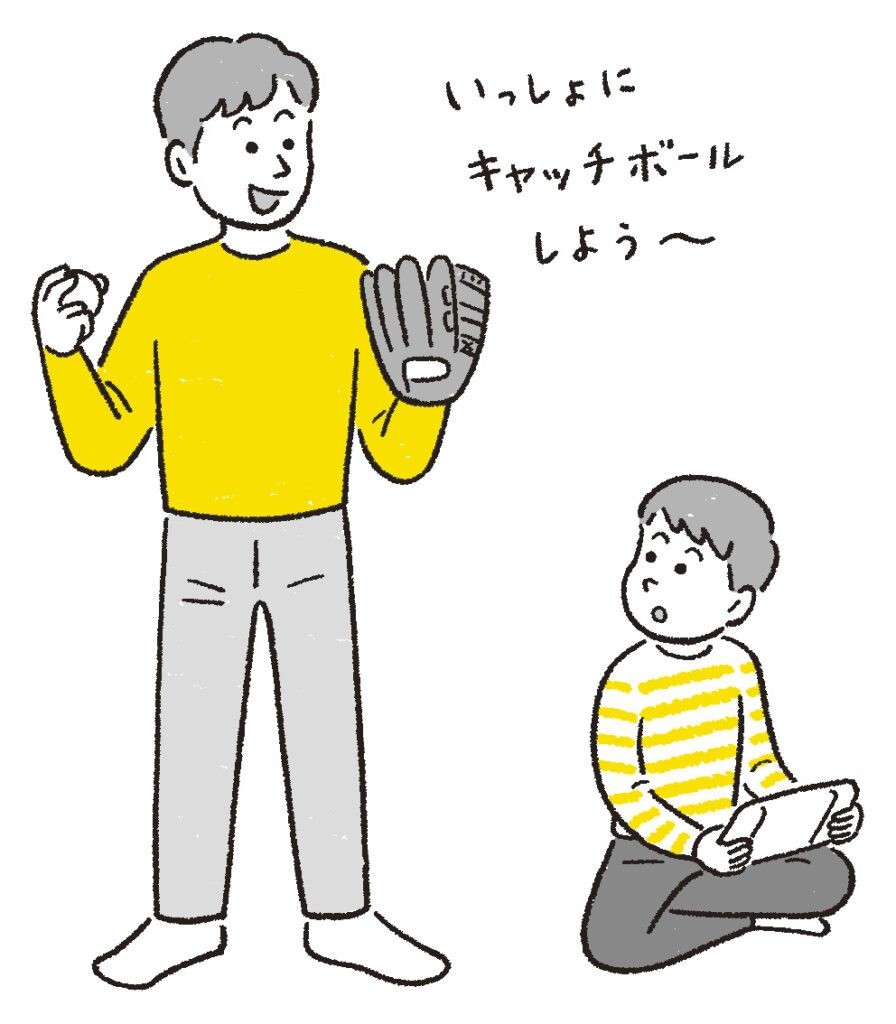
動画もゲームも、中毒性を高めるためにさまざまな工夫がされています。こどもの意思だけに頼ってコントロールするのは、不可能といってもいいでしょう。
ハマってしまったときは、無理に機器を取り上げると、さらに執着するので逆効果です。ほかに興味が持てることを提案する、保護者自身が、スマホをさわらないようにするなど工夫しましょう。
①時間の工夫~「おまけ時間」方式で、メリハリをつけて管理
一日の利用は1時間程度が適当です。ぶっ通しで使わず、こまめに時間を区切って遊ぶ、ゲーム時間を増やしてあげる日をつくるなど、メリハリをつけて管理しましょう。外出して気分をリフレッシュするのも効果的。どうしても機器をさわりたいときは、創作、学習系のアプリに切り替えても。
②金銭管理の工夫~課金=悪ではなく、上限を決めて
ゲームでは、課金をしていろいろなアイテムを持っている遊び仲間もいます。周囲に足並みをそろえる必要はありませんが、上限を決めて、ときには購入しても。システムをよく理解しないまま課金してしまうこともあるので、遊んでいる機器のクレジットカード決済機能はオフに。
③人間関係の工夫~家族だけでなく、親どうしのネットワークで管理
オンラインゲームは不特定多数の人とつながり、対戦や協力プレーができる機能があります。しかし、チャット内容から個人情報を特定したり、言葉巧みに誘い出したりする事例もあります。未成年はリアルな友達としかつながらないのが基本です。
依存してしまう理由があるかもしれないので、やみくもに禁止するのはNG
人間関係のトラブルや、学業不振、家庭不和などの不安や悩みの逃避行動として、ゲームや動画に没頭していることも。依存している背景を探ることも大切です。アクセスする頻度、時間が自制できず、寝食も忘れて最優先するような状態が1 年以上続く場合は「ゲーム依存」。専門外来へ相談を。
『こどもオレンジページNo.8』では、0~9歳のこどもたちとインターネットのかかわりに関する統計データや、専門家によるアドバイスを多数掲載しています。ぜひ書店やWEBでチェックしてみて♪
第1弾「本格的に使いはじめる前に知っておきたいこと」も参考に!
第2弾「動画とゲームを楽しむための3つのこと」も参考に!
◇監修/高橋暁子(たかはし・あきこ)さん
ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNS、10代のネット利用実態とトラブルに造詣が深く、先駆者として、安心な利用方法を啓発。著書に『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社α新書)など。

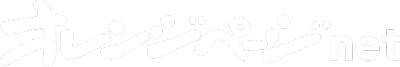 はこちら
はこちら
























